
ラジオ体操にとって欠かせないものとは何だろうか。もちろん、号令はあるべきですし、中には、ラジオ体操の歌を歌わないと気が済まないという方もいるでしょう。ただ、欠かせないものと言えば、やはり、ピアノ伴奏でしょう。現在、ラジオ体操のピアノ伴奏者は3人いますが、それぞれ個性や違いがあるのです。本日は、ラジオ体操のピアノ伴奏に注目します。
ラジオ体操のピアノ伴奏者3氏
ラジオ体操のピアノ伴奏者は3氏います。
※番組表を確認したところ、新年度・2022年度より、加藤由美子さんの出演がなくなりました。加藤さんは、第1体操と第2体操の間の首の運動の音楽に、季節の音楽を採用されており、私も、毎回楽しみにしていました。長い間、ありがとうございました。
幅しげみ氏
ラジオ体操のピアノ伴奏者と言えば、この人だと多くのラジオ体操愛好家は思っているでしょう。私も、そのように思っています。幅氏は、1981年からラジオ体操を担当されています。もう、大ベテランですね。また、テキスト付属のDVDやCDのピアノ伴奏も幅氏が担当です(当ブログ管理人調べ)。幅氏の特徴は、力強い演奏です。
朝のラジオ体操は、火曜日、金曜日を担当されています(巡回ラジオ体操時を除く)。
能條貴大氏
能條氏は、2018年からラジオ体操を担当されています。名川太郎氏の後任ということになりましょう。能條氏は、どちらかというと幅氏と似たような演奏スタイルだと感じます。
朝のラジオ体操は、月曜日、木曜日、土曜日を担当されています(巡回ラジオ体操時を除く)。
細貝柊氏
細貝氏は、2021年10月から、ラジオ体操のピアノ伴奏に加われました。男性のピアノ伴奏者は2人となります。
朝のラジオ体操は、水曜日、細貝を担当されます (巡回ラジオ体操時を除く) 。
なお、ラジオ(テレビ)体操の出演者に関する情報は「NHKラジオ体操、出演者」(外部リンク)で詳しく見ることができます。
(備考)名川太郎氏は、2018年度までラジオ体操のピアノ伴奏を担当されていました。名川氏の特徴は、優しい演奏でした。個人的には、一番好きなピアノ伴奏者でした。
また、加藤由美子氏は、2021年度までピアノ伴奏を担当されました。名川氏勇退のあとの推しは、加藤氏でした。少し寂しいです。
各伴奏者ごとに個性・違いがある

ピアノ伴奏者3氏が弾くラジオ体操は、全部同じだと思っている方が多いと思います。しかし、ピアノ伴奏者3氏それぞれ個性や違いがあります。確かに、先述の通り、「力強い演奏」や「優しい演奏」といったことは、正直聞き分けるのが難しいです。ただし、私たち一般人でも聞き分けることができるところも多々あります。
個人的に、各伴奏者に個性や違いがみられることは、とても面白いことだと思います。時には、ピアノ伴奏に注目しながら、ラジオ体操を行うことも面白いと思います。
個性・違いを聞き分けられるポイント(一覧)
それでは、個性や違いを聞き分けられる場所を見ていきましょう。なお、当ブログ管理人は、2級ラジオ体操指導士ですが、音楽についての知識はかなり疎く、説明がわかりにくいかもしれません。ご了承ください。
ラジオ体操第一
| 幅氏 | 能條氏 | 細貝氏 | |
| 前奏 1. 背伸びの運動 | 背伸びの運動に入る直前の音が低い | 背伸びの運動に入る直前の音が高い | 能條氏と同様 |
| 3. 腕を回す運動 4. 胸を開く運動 5. 横曲げの運動 | 胸を開く運動の直前にわずかながら間が空く | 胸を開く運動の直前にわずかながら間が空く 横曲げの運動に入る直前わずかながら間が空く | 胸を開く運動および横曲げの運動の直前に間は空かない |
| 9. 体を斜め下に曲げる運動 | 前の運動からこの運動に入るときの音が、隙間なく上がっていく(名川氏と同じ) | ||
| 12. 両足跳びの運動 | 伸びやか | 伸びやか |
そのほかの運動は、3氏ともにほぼ一緒のように感じる。
ラジオ体操第二
| 幅氏 | 能条氏 | 細貝氏 | |
| 7. ねじる運動 | 間がなく、高い音も入らない | 水平にねじるときに高い音が入る。 | 水平に左にねじるときと右にねじるときの中間にわずかな間がある |
| 9. 体をねじりそらす運動 | 斜め下に二度曲げるとき(2回目・3回目)間が空く | 斜め下に二度曲げるとき間が空かない(名川氏と同じ) | 斜め下に二度曲げるとき(1回目~4回目、全て)間が空く |
| 10. 体を倒す運動 | 腕を前に弱く振るとき間があかない | 幅氏と同様 | 腕を前に弱く振るとき間が空く |
そのほかの運動はほとんど違いがないと感じる。
以上の個性や違いを、是非、テレビやラジオ、動画等で確認していただきたいと思います。名川氏、加藤氏に関しては、皆さんで個性や違いを確認していただきたいと思います。
体だけでなく頭の体操にも
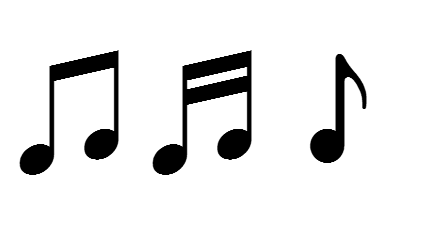
ラジオ体操が続かないという皆さん、時にはピアノ伴奏に注目しながらラジオ体操を行ってみるということもよいと思います。必ずやモチベーションアップにつながると思います。
また、愛好家の皆さんも、「今日のピアノ伴奏は幅さんだ。なぜなら~だからだ」と仲間に自慢するのもよいと思います。
ラジオ体操をしっかり行いながら、ピアノ伴奏は誰か聞き分けられると、体の体操だけでなく、頭の体操にもなります。みなさん、頑張りましょう。
